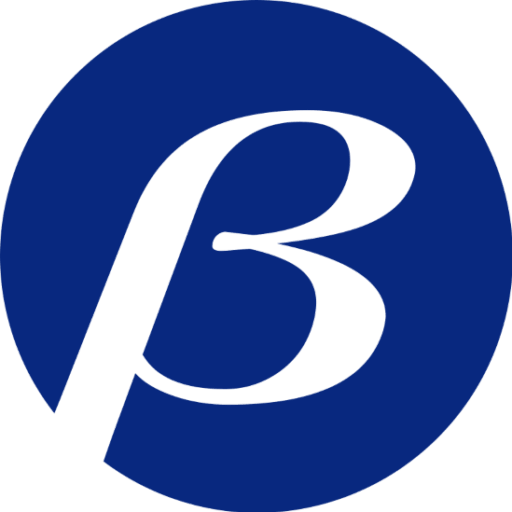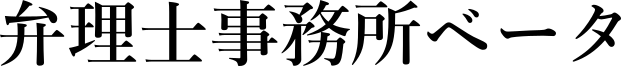謹んで新年のお慶びを申し上げます。旧年中は格別のご厚情を賜り誠にありがとうございました。昨年開業したばかりの弊所に温かいご支援をいただきましたこと心より感謝申し上げます。本年は開業二年目としてさらなる飛躍の年にしたいと考えております。特許においては、お客様の技術の本質を捉え、より強固な権利取得に貢献できるよう一層の研鑽を重ねてまいります。また、知的財産戦略についての知見を深め、お客様に多角的なご提案ができる事務所を目指してまいります。知的財産は、企業の競争力の源泉であり、イノベーションを支える重要な基盤です。その一翼を担う者として誠実かつ迅速な業務を心がけ、皆様のご期待にお応えできるよう精進いたします。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
-
年末のご挨拶
早いもので、今年も残りわずかとなりました。今年は弊所を開業しました。開業当初は不安もありましたが、多くの方に支えていただき、なんとか一年を乗り越えることができました。本当にありがとうございました。この一年は主に特許明細書の作成に取り組みながら日々勉強の連続でした。また、他の弁理士の先生方と共同で案件に取り組む機会にも恵まれ、新たな視点や経験を得ることができました。さらに、弁護士や公認会計士といった他士業の方々、そして様々な企業の方々との新たな出会いもあり、人とのつながりの大切さを実感した一年でもありました。来年もこのご縁を大切にしながら頑張ってまいります。引き続きよろしくお願いいたします。どうぞよいお年をお迎えください。
-
重粒子線治療装置

先日、重粒子線治療装置を見てきました。重粒子線治療装置とは放射線治療装置の一種で重粒子線を腫瘍に照射して治療するものです。放射線治療装置はエックス線やガンマ線を用いるものが普及しておりますが、この重粒子線治療装置は炭素イオンを光速の80%まで加速した重粒子線を用います。水素原子よりも重い炭素原子を使うことから重粒子線と呼ばれております。上記画像は重粒子線治療装置の一部を構成する回転ガントリと呼ばれるものです。直径11m、全長13mの巨大な円筒形の構造物です。この回転ガントリの内部に患者が配置され、患者の周囲を回転ガントリが回転することで、様々な方向から腫瘍に粒子線を照射することができます。以前仕事で関わっていたこともあり、回転ガントリの構造は熟知しているのですが、一度も実物を見たことがありませんでした。今回念願かなってようやく実物を拝見することができました。実物はやはり大きいですね。これでも超電導コイルを使って小型化したものです。世界初の重粒子線治療装置はドイツにあるもので、回転ガントリの全長は25mあります。それに比べれば約半分の大きさなので小型ということです。この回転ガントリが回転する姿も見ることができました。巨大な構造物がスムーズに回転する姿は感動ものでした。重機というより精密機械のような動きでした。下記画像は加速器と呼ばれるものです。これも重粒子線治療装置の一部を構成するもので、直径は約40m、全周が約130mあるリング状の構造物です。内部が真空のダクトの周囲にコイルが配置され、ダクト内を炭素イオンが飛翔します。これで加速された炭素イオンが回転ガントリまで運ばれ、患者に照射されます。これほど巨大な構造物でも埃ひとつ被っておらず、新品同様に手入れが行き届いていました。

-
浜離宮恩賜庭園

昨日と今日は弁理士試験の口述試験だったようですね。弁理士試験は、5月に実施される短答式と、6~7月に実施される論文試験と、10月に実施される口述試験の3つの段階に分かれています。口述試験は、試験官との直接対話なので私も非常に緊張しました。口述試験は、毎年プリンスパークタワー東京で開かれるのが恒例になっています。私の場合、午前中の試験だったので帰りに浜離宮恩賜庭園に寄ってきました。上記写真はそのときのものです。空がとても青かったことを覚えています。受験生の皆さまお疲れ様でした。
-
知財・情報フェア&コンファレンス

先日、東京ビックサイトで開催された知財・情報フェア&コンファレンスに行ってきました。毎年開かれる知財関連のイベントとしては国内最大級の見本市です。やはり注目だったのは生成AI関連の多さ。数年前はIPランドスケープ等のキーワードをよく聞いたのですが今年はあまり聞かなかったように思えます。ChatGPT、Claude、Gemini…生成AIの本体は米国の企業の独壇場で、国内の企業が追いつけるはずもなく、生成AIを応用した製品に留まっています。その製品でさえ、汎用生成AIの登場で同じ処理が可能になるとも言われており、国内の製品開発の存在意義が危ぶまれています。海外の巨大IT企業にまるで税金のように国内の富が吸い上げられる未来。或るブースの講演者が言っていた言葉、「それでも走り続けるしかない」というのが印象的でした。