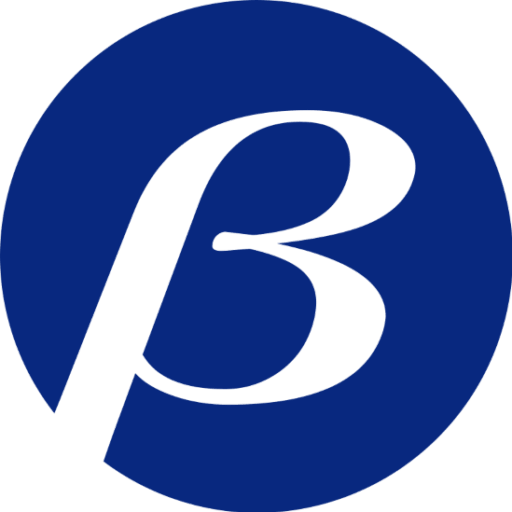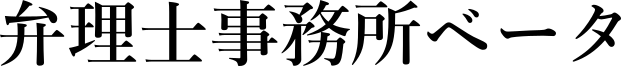ハイパーカミオカンデのお話の続き。地下空洞を見た後に地上に戻り山を見上げるとお城があるではないか!こんな飛騨の山奥にお城なんてあるんだ!と早速行ってみると神岡城というらしい。外見はとても古そうに見えたのだけど、実際は昭和45年に再建されたもの。内部は神岡町の歴史を紹介する展示館になっていました。

天守閣から見下ろす神岡町の風景は絶景でした。神岡町は中央に川が流れていますが、湧き水も豊富らしく、町を歩いていると側溝に相当な量の水が流れている。側溝に落ちたら溺れるんじゃないかと思えるくらいの水量。こんな山奥でも水には困らない町なんだろうな。

こちらは神岡城の隣に展示されている旧松葉家の内部。明治元年頃に建築された民家がそのまま展示されていました。初めて来たのにそんな気がしないのは昔の典型的な日本家屋の面影を残しているからだろう。1階は生活空間、屋根裏に相当する2階と3階は養蚕部屋だったらしい。私が子供の頃、祖母の家にも養蚕部屋がありました。部屋いっぱいにクワの葉が敷き詰められ、大量の蚕様がうねうねと動いている様子を今でも記憶しています。子供の頃は虫が平気だったので気持ち悪いとは思わなかったけど、今見たらだめかもしれない。

これは仁丹の自動販売機。旧松葉家で使っていたわけではないだろうから、たぶん展示場所としてここを使っているのだろう。正面側の上部に硬貨の投入口があり、正面側の下部に仁丹が出て来る穴が開いている。注目すべきは正面側の中央部の2つの穴。硬貨を投入してこの穴を覗くと風景の写真が何枚か見れたらしい。未だ写真が珍しかった時代。仁丹という商品を売るのに写真というメディアの提供をミックスさせている。写真見たさに仁丹を買った人も居たであろう。しかも仁丹の販売当初の明治30年代にこの自動販売機があったというから驚き。決して生活必需品ではない仁丹という商品をどうやって売ろうか、当時の仁丹の販売会社の意気込みが感じられる。百年続く企業になるわけだ。