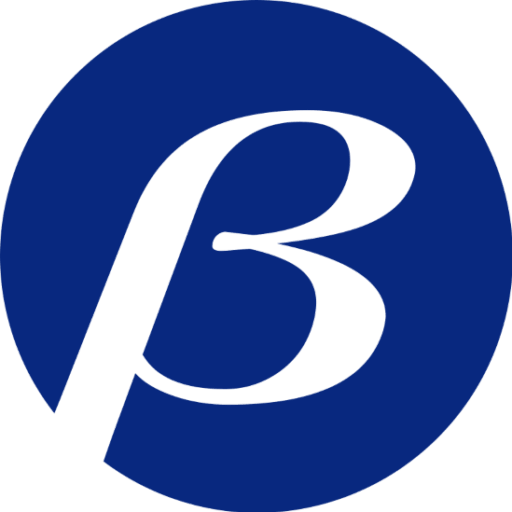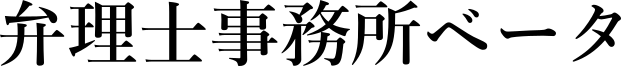令和8年4月1日施行 著作権法の一部を改正する法律(令和五年法律第三十三号)
「著作権者不明等の場合の裁定制度」というものがあります。利用したい著作物があるときにその著作権者の所在が不明な場合があります。そのような場合に文化庁長官の裁定を受けることで著作物の利用ができるという制度です。但し、補償金の供託が必要です。従来からこの制度はありましたが、さらに利用し易いものになります。
・未管理公表著作物等の利用(改正後の著作権法第67条の3)
インタ―ネット等の発展により、プロの作家ではなく、一般の方が創作した著作物が広く配布される事例が増加しております。これらの著作物の中には、著作権者が不明、または著作権の所在が特定し難い場合があります。そのような場合、著作権者と連絡がとれず、円滑な利用ができないことが課題でありました。そこで、このような著作物について、適法な利用を促し、それにより発生した対価を著作権者に還元するために、新たな裁定制度が創設されます。本制度は、集中管理がされておらず著作権者の意思が明確でない著作物(未管理公表著作物等)について、文化庁長官の裁定を受け、補償金を支払うことで、その著作物の利用が可能となるものです。従来の裁定制度と違う点は、3年を上限とする時限的な制限がある点、著作権者が現われた場合、その著作権者は裁定の取り消しを請求することができる点です。3年を経過した後は再度申請することで更新が可能です。また、従来の裁定制度では一度裁定を受けることができれば、その著作物をずっと利用し続けることできましたが、新制度では著作権者が現われた場合、その著作権者により利用の停止を求められるかもしれないことになります。著作権者が現われたならば、その著作権者とライセンス交渉等ができるだろうから、著作権者の権利保護を優先したものと思われます。裁定制度により著作物を利用する者は、その点の注意が必要かもしれません。
・指定補償金管理機関及び登録確認機関(改正後の著作権法第104条の18,第104条の33)
裁定制度を利用する者は、これまでは文化庁に直接手続きをとっていました。しかし、法改正後は、文化庁長官による指定・登録を受けた民間機関が窓口となり、この民間機関を介して文化庁に申請をすることになります。手続の簡素化・迅速化を実現する趣旨のようです。指定補償金管理機関及び登録確認機関の2つの機関が設けられます。裁定制度の利用者が支払った補償金は、指定補償金管理機関に預けられます。裁定後に著作権者が現れた場合、指定補償金管理機関は、預けられた補償金を著作権者に支払います。利用したい著作物について、その利用の可否に関する著作権者の意思が確認できない場合、まずは登録確認機関に新たな裁定の申請を行います。申請を受け付けた登録確認機関は、その申請について要件の確認や使用料算出の事務を行い、文化庁に取り次ぎます。現行法の「一般社団法人図書館等公衆送信補償金管理協会(SARLIB)」のような機関が設立されるようです。指定補償金管理機関は「全国を通じて一個に限り」と規定されているのに対し、登録確認機関はそのように規定されていないので、複数個設立されるようです。